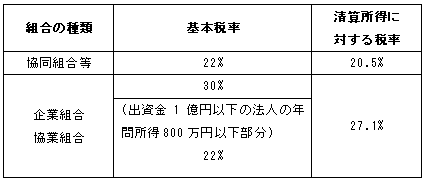組合に関する特別税制は、前述のように主として事業協同組合等に関するもので、以下に説明するものは、特にその旨ことわりのあるものを除き企業組合及び協業組合には適用されない。また、前記「I組合に関する税制の概要」欄で説明した以上に説明を要しないものは省略する。
1.法人税率の軽減(法人66条、99条、経済16条)
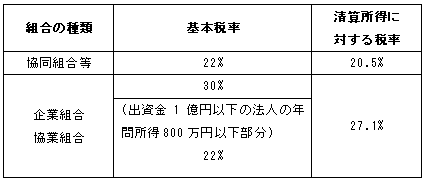
〔備考〕
清算所得=残余財産価額一(資本等金額十利益積立金額等)(法人93条)
2.加入金の益金不算入(法人22条、2条16号〜17号)
(企業組合及び協業組合にも適用)
法人税の課税対象となる各事業年度の所得を計算する場合の益金には、「資本等取引」に係るものを含まないことが定められている(法人22条2項)。
「資本等取引」とは、法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引であり(法人22条5項)、「資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と「資本積立金額」との合計額である(法人2条16号)。そして、「資本積立金額」には協同組合等その他政令で定める法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額が含まれることになっている(法人2条17号ハ)。
したがって、加入金は、資本等取引に係るものに該当し、益金とはならない。また、企業組合及び協業組合は、上記政令で定める法人として指定されており(法人令8条)、この適用を受けることになっている。なお、この加入金とは、持分調整金であって、権利金的なものは含まれないことに注意しなければならない(基通(法)1-5-2)。
〔備考〕加入金(基通(法)1-5-2)
法人2条17号ハ(資本積立金額の意義)に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。
3.事業利用分量配入当の損金算(法人61条)
事業協同組合等において組合の事業を利用した分量に応じて行う事業利用分量配当は、損金に算入される。この場合の分配の基準となる組合員の事業利用高は、当期の利用高に限られ、当期前のものは含まれない、また、対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用したことによって生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合事業であっても組合員の利用がないと認められる事業から生じた利益は対象にならない。
事業利用分量配当は、配当という字句が使われているが、所得税法上の配当所得とは認められず、支払時における源泉徴収及び受領組合員の配当控除は適用されない。
一方、企業組合の従事分量配当については、損金算入が認められていない。組合員が企業組合から受ける従事分量配当は配当所得とされているので(所得令62条)、配当に当たっては20%の源泉徴収を行う必要がある(所得182条2号)。
また、協業組合についても、出資配当以外の配当はすべて配当所得とされており(所得令62条)、源泉徴収を行う必要がある。
なお、当期前の所得の留保額(利益積立金など)に係る事業利用分量配当は、配当所得とされる(個別通達昭44.5.26直審(法)29)。
〔備考〕事業分量配当の対象となる剰余金(基通(法)14-2-1)
法人61条1項1号(事業分量分配金)に規定する事業分量に応ずる分配は、その剰余金が協同組合等と組合員その他の構成員との取引及びその取引を基礎として行われた取引により生じた剰余金から成る部分の分配に限るのであるから、固定資産の処分等による剰余金、自営事業を営む協同組合等の当該自営事業から生じた剰余金のように組合員その他の構成員との取引に基づかない取引による剰余金の分配は、これに該当しないことに留意する。
(注)事業分量配当又は従事分量配当に該当しない剰余金の分配は、組合員等については配当に該当する。
4.賦課金の仮受金経理(基通(法)14-2-9)
教育事業及び指導事業に充てるために賦課した賦課金について、当該事業が翌事業年度に繰り越されたため剰余が生じた場合には、これを翌年度の経費に充当するため仮受金等として経理し、益金に算入しないことができる。したがって、この適用を受ける賦課金の範囲以外の賦課金は、例え賦課金の名称をもっていても適用を受けられないし、また、本制度の適用を受ける賦課金でまかなうべき費用を他の事業収入等でまかない、そのために賦課金に残余がでてもその部分は仮受の対象にならないことになっている。
なお、仮受の対象となる賦課金は教育・指導事業に充てるものに限られているので、それ以外の費用に充てるための賦課金がある場合は、徴収の段階(収支予算)から区分して経理する必要がある。また、一般管理費など共通費として徴収する賦課金については、例えそのなかに教育・指導事業に係るものが含まれていてもそのままでは仮受の対象にならないが、これを教育・指導事業に区分、配賦すれば対象となる。
〔備考〕協同組合等の特別の賦課金(基通(法)14-2-9)
協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。
5.一留保所得の特別控除(租特61条)
事業協同組合等が、その所得の全部又は一部を留保したときは、期末利益積立金額(当該事業年度で留保した金額を含む。)が出資総額の4分の1に達するまで、一定金額を損金に算入することができる。
- 対象者
(1)事業協同組合
(2)事業協同小組合
(3)協同組合連合会(中協法9条の9-1項1号又は3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)
(4〕出資商工組合・同連合会
(5〕出資生活衡生同業組合・同連合会
- 適用条件
員外利用が20%以内であること。
〔備考〕
1.員外利用割合が20%を超えるかどうかの判定(租通(法)61-12)
租特61条2項に規定する組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における組合員等の事業の利用分量の額の100分の20(租特令37条4項に規定する事業については、同項に規定する割合。以下租通(法)61-13において同じ。)を超えるかどうかは、次に掲げる法人の種別に応じ、それぞれに掲げる事業(当該事業に付帯する事業を含む。)の区分に応じて判定するものとする。
(1)商工組合については、中団法17条2項1号から3号'までの各号の区分。ただし、同項3号の事業については、体育施設又は教養文化施設に係る事業とその他の事業との区分()、(3)において同じ。)
(2)商工組合連合会については、中団法33条において準用する同法17条2項1号から4号までの各号の区分
(3)事業協同組合及び事業協同小組合については、中協法9条の2-1項1号から5号までの各号の区分
(4)事業協同組合連合会については、中協法9条の9-1項2号及び4号から7号までの各号の区分
(5)「生活街生同業組合については、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律8条1項4号から10号までの各号の区分
(6)生活街生同業組合連合会については、生活衡生関係営業の運営の適正化及び
振興に関する法律54条3号から9号までの各号の区分
2. 2以上の事業を行う組合についての員外利用割合の判定(租通(法)61-13)
租通(法)61-12の場合において、2以上の事業の区分に属する事業を行う組合について、そのいずれか一の区分に属する事業につき組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における組合員等の事業の利用分量の額の100分の20を超えることとなるときは、当該組合については租特61条1項の規定の適用がないことに留意する。
3. 事業の利用分量の額の判定の基礎となる金額(租通(法)61-14)
租特61条2項に規定する事業の利用分量の額は、各事業年度ごとに、例えば資金の貸付事業については貸付金額の積数(積数の計算が困難である場合には、各月末の平均残額。以下同じ。)、貯金若しくは定期積金の受入事業については貯金若しくは定期積金の額の積数、物資の供給事業については販売高、共同施設利用事業については利用料、医療事業については医擦費等その事業の内容に応ずる合理的な某準により判定するものとする。
4. 中協法及び中団法の改正(昭59)により、員外利用の制限について特例措置を受けた組合については、本措置の適用が認められる。
〔備考〕中協法及び中団法の改正(昭59)の主な改正点
1.団地組合の立ち上がり期に係る特例
2.組合員の脱退に係る特例
3.地域住民等」般公衆への施設の開放に係る特例
- 損金算入限度額(租特令37条)
(1)控除対象留保金額
当該事業年度の所得金額から、次の1)〜4)の金額を控除した金額が控除対象留保金額となる。
ただし、この制度が適用されるのは利益積立金額が出資総額の4分の1までの組合であり、当期において出資総額の4分の1を超えることになる場合には、超える部分を控除した留保金額が対象となる。
1)配当、賞与など当該剰余金処分により支出されるもの
2)社外流出額(別表四「29の(3)」)
3)〔 1)+2)+(当該所得金額−( 1)+2) ))×68%〕に対する法人税額
4) 3)の法人税額に係る道府県民税及び市町村民税額
(2)特別控除額
控除対象留保金額x32%
4.留保金の取崩し
3年以内に配当及び益金処分の賞与として取り崩したときは、古い年度の留保金より益金に算入される。
5.適用期問
平成17年3月31Hまで
(注)平成17年度税制改正において、適用期限が2年延長される予定
6.火災共済協同組合等の異常危険準備金の損金算入(租特57条の5、租特令33条の5)
青色中告書を提出する火災共済協1司組合等が、各事業年度において異常災害損失の補てんに充てるため、異常危険準備金を積み立てたときは、下記の金額を損金に算入することができる。
- 対象者
(1)火災共済協同組合・同連合会
(2)出資生活衛生同業組合・同連合会
- 損金算入限度額
正味収入共済掛金の5%
- 準備金の取崩し
(1)異常災害損失が生じた場合
その金額に相当する金額を益金に算入する。
(2)繰り越された準備金のうち10年以前に積み立てた額がある場合次のいずれか低い金額を益金に算入する。
1)10年以前に積み立てた金額
2)異常災害の生じた年の繰越異常危険準備金と新規に積み立てた金額の合計額から当年度保険料の60%(連合会は75%)を控除した金額
(3)解散、共済事業の廃止の場合
当該解散又は廃止の日における異常危険準備金の金額
(4) (1)、(2)、(3)以外で取り崩した場合
当該取り崩した日における当該共済に係る準備金の金額のうち、取り崩した金額に相当する金額
〔備考〕
1.火災共済協同組合の共済掛金は、損害保険料控除の対象となっており、他の損害保険料と合算し、短期については3、000円まで、10年以上の長期については15、000円まで、所得控除が認められている(所得77条、所得令214条)。
2.異常災害損失は各年度において支払った、又は支払うべきことの確定した共済金の総額が当該年度における正味収入掛金に75%(連合会は90%)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3.対象となる共済の範囲(租特令33条の5)
4.出資生活衛生同業組合・連合会が積み立てる火災に係る共済事業の支払準備金については正味収入共済掛金の2.5%の損金算入が認められる。
- 適用期間
平成19年3月31日まで
7.生命傷害共済事業に係る責任準備金及び支払準備金の損金算入
(個別通達(法)昭51.4.13直法2-11)
事業協同組合・同連合会が、所管行政庁から承認を受けた事業方法書、普通共済約款、共済掛金算出方法書に基づき行う生命傷害、白動車事故見舞金及び白家用白動車の各共済事業並びにこれらに係る再共済事業に関して積立てた責任準備金及び支払準備金は、損金に算入される。
〔備考〕
損金算人については、個別通達(法)昭28.7.14直法1-81「法人税法施行規則の一部を改正する政令の施行に伴う法人税の取扱について」の「1、2、3、5、11」の取扱いに準じて扱われる。
8.事業税率の軽減(地方72条の24の7、地方附則40条10項)
- 対象者
(1)中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
(2)出資商工組合・同連合会
(3)商店街振興組合・同連合会
(4)出資生活衛生同業組合・同連合会、出資生活衡小同業小組合
- 標準税率
所得のうち年400万円以下の金額 … 5%
所得のうち年400万円超の金額、及び清算所得 … 6.6%
〔備考〕一般法人の標準税率
所得のうち年400万円以下の金額 … 5%
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 … 7.3%
所得のうち年800万円超の金額、及び清算所得 … 9.6%
|